豊田小原和紙工芸について
About


豊田小原和紙工芸とは?
About
室町時代より、西三河地方では「三河森下紙」という番傘や障子紙用として用いられる和紙の生産が盛んでしたが明治の頃、近代産業の煽りを受けて和紙のニーズは衰退の一歩を辿っていました。そんな状況の中、当時の小原村では、三河森下紙を残してゆく活動が行われておりました。ある時、愛知県碧南市出身の芸術家藤井達吉が三河森下紙厚物を発注した事で、小原和紙が持つ魅力に感銘を受け、小原和紙についてより詳しく知る為に小原に訪れる機会がありました。藤井先生は小原にて和紙の新たな可能性を模索していく中で和紙を産業として発展させる必要性を説きました。「三河森下紙」は当時商品として見られていましたが、藤井先生による染色や一閑張の技術の伝授によって和紙工芸としての道を歩み始めたのです。藤井先生や過去の作家達により小原にて育まれてきた豊田市の伝統和紙工芸。それが現在の「豊田小原和紙工芸」なのです。

伝統を広める、
豊田小原和紙のふるさと
株式会社美術生活では豊田小原和紙を広める活動を行っております。当社代表の山内も運営に携わっている「和紙のふるさと」では、豊田小原和紙の魅力を多くの方々に知っていただけるように豊田小原和紙の手作り体験と作品の鑑賞などが可能です。
もしご興味がございましたら、お気軽にお越しください。
公式HPを見る
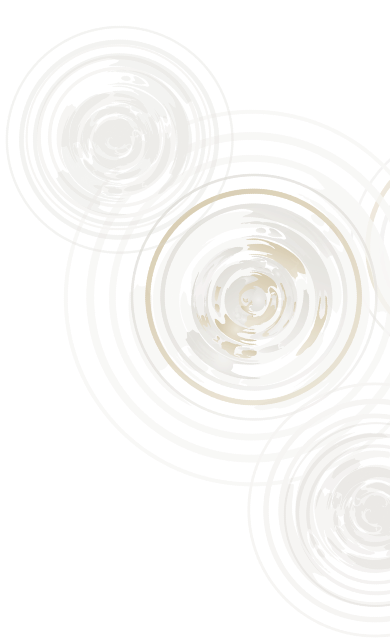
豊田小原和紙工芸の魅力
Charm

手作りの温もりと質感
伝統的な手法で一枚一枚丁寧に作られています。また楮の繊維を主原料とすることから、非常に丈夫で長持ちします。また、柔軟性が高いため、曲げたり折ったりしても破れにくいのが特徴です。その為、襖・ランプシェードなど多岐にわたる用途で使用されています。
環境にやさしい素材
和紙原料のコウゾなど自然植物の繊維を使用し、環境に優しく肌にも優しい和紙は素材としても高く評価されています。使用後も自然と元に戻りやすくという点が、現代の持続可能な消費にもつながります。


豊田小原和紙ができるまで
Flow
STEP 1
原料の準備
主に楮(コウゾ)の植物繊維が使われます。楮はまず収穫され、皮を剥がしてから、繊維を抽出するために煮沸されます。

STEP 2
繊維の処理
煮沸した繊維は、灰汁(あく)で洗浄されて不純物を除去し、さらにたたいて柔らかくし、繊維を分解します。この過程で繊維が均一になり、紙の品質に影響します。

STEP 3
紙漉き(すき)
処理された繊維は水槽に移し、水と繊維がよく混ぜられます。繊維が均等に分布するように枠を振動させます。これにより、繊維が水面に均一に広がり、紙のベースが作られます。

STEP 4
乾燥
ベースが形成された後、余分な水分を抜くために軽く圧縮されます。その後、ベースは木製の板や窓ガラスなどに貼り付けられ、自然乾燥させます。




